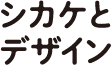デザインの立ち位置はどこに?|「エスカレーター、立つのは右?左?」
時間があるときや、出張の合間などに、ふらっと美術館や博物館に立ち寄ることがあります。
たとえば美術館で、作品を間近で見ると伝わってくる生々しい力強さ。
筆の跡や絵の具の厚みから、作者の息づかいのようなものを感じます。
一方で、少し離れて眺めると、色彩の流れや構図の意図が見えてくる。
近くで感じる熱と、遠くから見る全体像の両方があってこそ、作品の魅力が伝わる気がします。
そう考えると、
エスカレーターの「立つ位置」も似ているかもしれません。
大阪では右、東京では左。
当たり前だと思っていたことが、地域によってまったく違うのです。
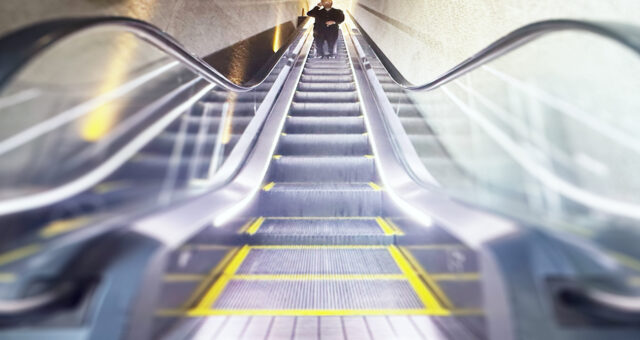
どちらが正しいというわけではなく、
その土地の“空気感”や“慣れ”の中で自然と定着したもの。
人は理屈よりも、周囲の流れに合わせて動くものなんですね。
この違いから感じるのは、
「人の行動や感じ方は、文脈によって変わる」
ということ。
同じ景色でも、立つ位置や見る角度が違えば印象が変わる。
それはデザインやマーケティングにも通じます。
どんなに完成されたデザインでも、
受け取る人の環境や文化が変われば見え方は変わる。
大事なのは「どんな人に、どんな文脈で響くデザインか」という視点です。
まとめ
・習慣は理屈より空気で決まる
・地域や文化で“普通”は変わる
・デザインも文脈を読むことから始まる
おすすめの本
「正しい」とは何か?: 武田教授の眠れない講義
武田邦彦 著 / 小学館 / 2013
社会・時代・立場によって変わる「正しさ」の本質を、具体例を交えてわかりやすく語った一冊。
「正解」ではなく、「選ばれる正しさ」を考えるヒントになるかもしれません。
FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣
ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド 著 / 上杉 周作、関 美和 翻訳 / 日経BP / 2019
→ 世界の見方をデータとともに考え直す本。文化や視点の違いを浮き彫りにしてくれる。
学校広報について
学校広報でも、地域や校風によって“伝わり方”は変わります。
同じキャッチコピーでも、
都市部の高校と地方の高校では響き方が違う。
「文脈を読む力」は、
デザインにも教育にも共通する大切な視点だと思います。